[CD-R盤]
ラフマニノフ/交響曲第2番 ホ短調 OP.27
レオポルド・ストコフスキー指揮 ハリウッド・ボウル交響楽団
ロサンゼルス近郊の有名な野外ホール、ハリウッド・ボウルにおけるライヴ録音。
米マサチューセッツ州在住のエアチェック・コレクターの提供音源。ただし、エアチェックではなく放送局による保管音源のコピーと思われる。
テープ録音導入前のアセテート・ディスク・レコーダー(33・1/3回転の16インチ盤1枚で20分程度録音が可能だった)による録音だが、ディスクの保存状態が良好だったためか、第3楽章冒頭にスクラッチノイズがかすかに聞こえる以外にノイズもなく、ディスク録音とはにわかに信じられない高音質。野外というハンディキャップも感じさせず、巧みなマイクセッティングを行っているのであろうか、バランスも良好で弦の美しさや金管の輝かしさなど、モノラルながら鑑賞には全く不満がない。
ストコフスキーが録音に造詣が深いことはよく知られており、レコード化を前提としない放送録音にまで関与していたかは不明だが、事前に注文を付けていた可能性はある。演奏終了後、拍手の音質の古さでようやく1946年という年代に気付く(野外のためマイクが客席から遠いこともある)。かつて海外盤で同一の音源がCD化されていたが、当音源はさらに音質が良いと思われる。
ラフマニノフの交響曲第2番は、いかにもストコフスキーにふさわしい作品。しかし長いレコーディング・キャリアの中で録音機会がなく、最晩年の1977年にCBS へのレコーディング予定がありながら、惜しくも録音数日前に95歳で亡くなり、正式なスタジオ録音は実現せずに終わった。当ディスクの演奏後、亡くなるまでの約30年間にレコーディング計画がなかったことが不思議だが、ストコフスキーという人は、一般に認識されるような大衆向けのエンターテイナーというよりも(その要素も多分にあるが)、現代音楽の初演を数多く手がけたり、新しい録音方式に関心を示したり、オーケストラ配置を大胆に変更したように、あくまで実験的・啓蒙的発想で聴衆に音楽を届けるスタンスだったのだろう。その意味では、過去指向的なラフマニノフの交響曲第2番にはあまり興味がなかったとも考えられる。とはいうものの、当ディスクに聴く演奏は、ストコフスキーらしさ全開の豪華絢爛を極めたものとなっている。
ちなみに、演奏しているハリウッド・ボウル響は、1945年にストコフスキー自らが設立した団体で、1950年代中期からカーメン・ドラゴンが指揮した同名のライト・ミュージック中心の団体(米キャピトル・レーベルに録音する際にはキャピトル響とも称した)とは別団体。ただし、わずか2年でコンサート活動を休止し、その後は1960年代までレコーディング専門の団体として存続したと言われる。いずれにしても楽員は専属ではなく、演奏会やレコーディングの度に契約するフリーランスだったと考えられ、コンサート活動休止後は、メンバーの一部ないし多くがカーメン・ドラゴン指揮の団体に参加したこともあったのだろう。ハリウッド周辺には複数の紛らわしい名称のオーケストラがあり、ブルーノ・ワルターやストラヴィンスキーのために編成されたコロンビア響とロサンゼルス・フィルとの関係や、ハリウッドの映画音楽関係者が関わったと言われるグレンデイル響と(カーメン・ドラゴンの)ハリウッド・ボウル響の関係なども含め、よく分からないことが多い。
ストコフスキーは、1940年にフィラデルフィア管弦楽団の常任指揮者を退任後、オール・アメリカン・ユース管、ニューヨーク・シティ響、ハリウッド・ボウル響と団体を次々と設立するものの、フィラデルフィア管時代のような経営的安定を確保出来ないため長続きせず(第二次世界大戦前後という事情もあったが)、キャリア的には模索の時期だったかもしれない。その後は、ニューヨーク・フィル、ヒューストン響などのポストを経て、1962年のアメリカ響設立によりオーケストラ遍歴は落ち着くことになる。
ストコフスキーは上記のように、ラフマニノフの交響曲第2番のスタジオ録音を残さず、当ディスクのライヴが現在確認されている唯一の録音である。
※総合カタログは下記を参照下さい:
https://www.ne.jp/asahi/classical/disc/index2.html
*【ご注意】
当商品はCD-R盤です。CD-Rは通常の音楽CDとは記録方法が異なり、直射日光が当たる場所、高温・多湿の場所で保管すると再生出来なくなる恐れがあります。
また、CD・DVD・SACD再生兼用のユニバーサルプレーヤーや、1990年代以前製造の旧型CDプレーヤーなどでは再生出来ない場合がありますが、メーカーや機種の異なるプレーヤーでは再生出来ることもありますので、複数のプレーヤーをお持ちの場合はお試し下さい。
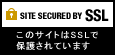

![画像1: [新品CD-R] PREMIERE ストコフスキー&ハリウッド・ボウル響/ラフマニノフ 交響曲第2番](https://www.maestrogarage.com/data/maestrogarage/_/70726f647563742f6364725f707265363031303064665f312e6a7067003330300000660066.jpg)
![画像2: [新品CD-R] PREMIERE ストコフスキー&ハリウッド・ボウル響/ラフマニノフ 交響曲第2番](https://www.maestrogarage.com/data/maestrogarage/_/70726f647563742f6364725f707265363031303064665f322e6a7067003330300000660066.jpg)